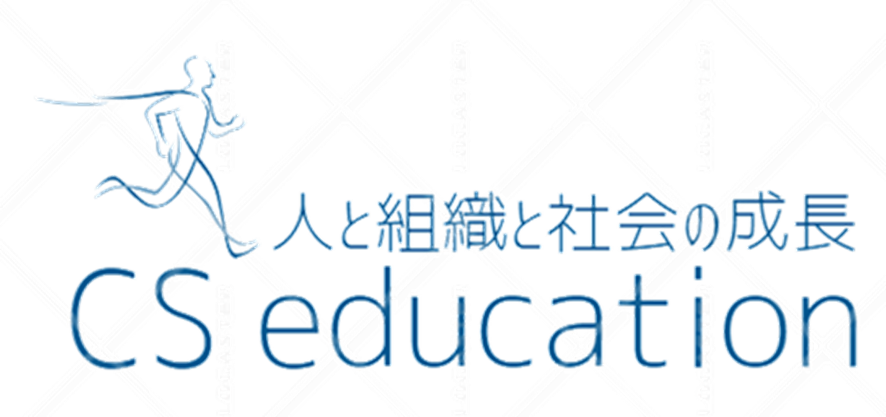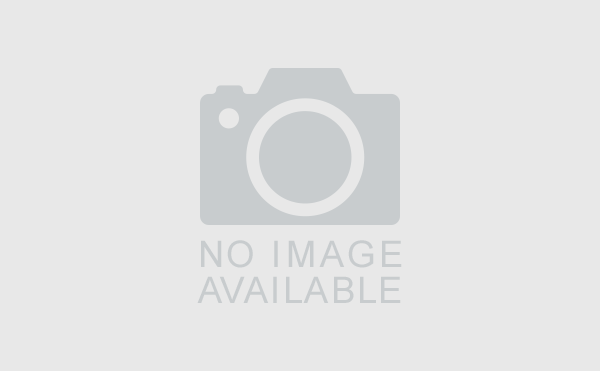【過敏状態?】ハラスメントをどう受け止めるか

ハラスメントを気にしすぎ?
目次
近年、職場や学校、家庭など、さまざまな場面でハラスメントに対する関心が高まっています。モラルハラスメント(モラハラ)、パワーハラスメント(パワハラ)、セクシュアルハラスメント(セクハラ)など、多くのハラスメントの形態が認識され、その防止策が求められています。しかし、こうした取り組みが進む中で、ハラスメントを気にしすぎているのではないかと感じることはないでしょうか?今回は、ハラスメントに対する過度な意識がもたらす影響について考えてみたいと思います
過剰なハラスメント意識の影響

当ブログでも何回もお伝えしていますが、ハラスメント行為は許される事ではありません。しかしながら、中には「この行為はハラスメントになるのではないか?」と考え、人との接触を過度に減らす方がいます。
ハラスメント意識が高まることは、良い事ではありますが、過敏に反応しすぎると悪影響も出てくることがあります。
コミュニケーションの萎縮
ハラスメントを過度に恐れるあまり、職場でのコミュニケーションが萎縮してしまうことがあります。上司や同僚が互いに注意深くなりすぎ、自然な対話やフィードバックが難しくなる場合があります。結果として、チームの連携が悪化し、生産性が低下することもあります。
ユーモアの喪失
ユーモアや軽い冗談がハラスメントと見なされることを恐れるあまり、職場の雰囲気が硬直化することがあります。適度なユーモアは、ストレスの軽減やチームの結束を強める効果がありますが、ハラスメントを恐れることでこれらの効果が失われることがあります。
昨今では、軽い冗談であっても相手の受け取り方によっては、ハラスメントになりかねないため、冗談を言わない様に指導を行う企業もあります。
自己検閲の増加
ハラスメントに対する過度な意識は、個々人が自己検閲を強化する原因となることがあります。自己検閲が強まると、自分の意見や考えを率直に表明することが難しくなり、組織全体の創造性や革新性が阻害される可能性があります。
若手社員は、自分の意見が受け入れられるか、上席者は自身の発言がハラスメントとして認識されるのではないか、などそれぞれが疑心暗鬼となり、信頼関係の構築にも影響が及ぶことがあります。

不当な告発のリスク
ハラスメントに対する過敏な対応は、不当な告発や誤解を招くこともあります。誤った告発が広がると、無実の人々が不必要なストレスを受け、職場の環境が一層悪化する可能性があります。
酷い場合には、嫌いな人や気に食わない人を陥れるために、モラハラやセクハラの被害をでっち上げ、告発するなどもあります。
バランスの取れた対応の重要性
ハラスメントを防ぐための意識向上は重要ですが、それが過剰になりすぎると逆効果になることがあります。以下に、バランスの取れた対応を実現するためのポイントを挙げます。
明確なガイドラインの設定
ハラスメントの基準や対応方法について、明確で具体的なガイドラインを設けることが重要です。曖昧な基準ではなく、具体的な例を示すことで、誤解を減らし、適切な行動を促進します。
特に指導においては、厳しい指摘をしなければならない場合もあります。言葉遣いも重要ですが、必要な指導が行えるような環境構築が求められます。
信頼関係の構築
職場でオープンなコミュニケーションを推進し、ハラスメントの疑いや懸念について自由に話し合える環境を整えることが重要です。これにより、信頼関係を構築しやすく、早期に問題を発見・解決し、誤解を防ぐことができます。
チームビルディングなどを取り入れ、積極的なコミュニケーションが取れる場を作ることが大切です。
教育とトレーニングの実施
ハラスメントに対する正しい理解を深めるための教育やトレーニングを定期的に実施することが有効です。ハラスメントの不当な告発などは、ハラスメントの知識が不足しているがために起こることが多いです。またコミュニケーションの機会を提供するなど、ハラスメントの知識だけでなく、人間関係の構築につながる取り組みも重要です。
ハラスメント教育を行い、適切な行動を促進し、過度な恐れを和らげることが大切です。
まとめ
ハラスメントに対する意識を高めることは重要ですが、過度な恐れや過敏な対応は逆効果になることがあります。バランスの取れたアプローチを実現することで、健全なコミュニケーションと働きやすい環境を維持することが可能です。正しい知識と柔軟な対応を通じて、ハラスメントの問題を適切に解決していきましょう。
当社では、ハラスメント全体に対するセミナー・研修を開催しています。ご興味のある方は、ぜひ一度当社の研修やセミナーを受講してください。研修依頼は、お問合せフォームからご連絡ください。